
「地味な仕事に、光る人がいる」
部下を持つようになって、ある法則に気づきました。周囲から高い評価を受ける人には、誰も気づかないところで続けている**”見えない努力”**があるんです。
この記事では、製造現場からWeb担当に転身した私の経験から、なぜか評価が上がる人に共通する習慣と、明日から実践できるコツをお伝えします。
目次
- 「目立たない努力」が生む確かな評価
- なぜか評価が上がる人に共通する3つの習慣
- 今日から始められる「見えない努力」の実践方法
- なぜ「見えない努力」は評価につながるのか
- まとめ:小さな習慣が大きな評価を生む
「目立たない努力」が生む確かな評価
「たかっちさん、Cさんってすごくないですか?」 「え?どんなところが?」 「なんか、困ったことがあると、さりげなく解決してるんですよ」
製造現場のリーダーだった頃のこと。若手社員からこんな言葉を聞きました。
確かに、Cさんの周りではトラブルが少なかった。派手な成果を上げる訳でもない。ただ、なぜか現場が回っている。
ある日、早めに出社した時のこと。誰もいない工場で、Cさんが一人、機械の点検をしていました。
「おはよう。今日も早いね」 「あ、たかっちさん。ちょっとした違和感があったので」
その「ちょっとした違和感」が、大きなトラブルを未然に防いでいたことを、後で知りました。
Web担当に異動してからも、似たような場面に出会います。若手社員のDくん。アクセス数が急に伸びた時、さりげなく教えてくれました。
「ここの数字、いつもと違う動きしてますよ」
その一言がきっかけで、重要な傾向を発見することができたのです。
なぜか評価が上がる人に共通する3つの習慣
私が観察してきた「評価が上がる人」には、3つの共通点がありました。ぜひあなたも取り入れてみてください。
1. 「予防」の習慣
小さな違和感を見逃さない
評価される人は、問題が大きくなる前に動きます。彼らは「何か変だな」という微細な感覚を大切にします。
製造現場のCさんは、機械の音の微妙な変化に気づいていました。それは数値では表れない、経験に基づく「感覚」でした。
Web担当のDくんは、通常と少しだけ異なるアクセスパターンに気づき、それを伝えてくれました。
問題が起きる前に動く
評価される人は「事後対応」ではなく「予防」に力を入れています。問題が小さいうちに対処することで、大きなトラブルを防いでいるのです。
日々の点検を欠かさない
これは単なる「念のため」ではなく、システム化された習慣です。Cさんは毎朝、担当機械を同じ順序でチェックしていました。Dくんはアクセス解析の特定の指標を毎日確認する習慣がありました。
2. 「気づき」の習慣
データの変化を敏感に察知する
評価される人は、数字やデータの「普段との違い」に敏感です。Web担当のDくんは、わずか5%のアクセス増加にも気づいていました。
「これくらいの変化なら…」と見過ごしにせず、何かのシグナルかもしれないと考える習慣があります。
周りの人の様子を観察する
人の表情や雰囲気の変化にも敏感です。「今日の〇〇さん、なんだか元気がないな」という気づきが、重要な問題の早期発見につながることも。
「いつもと違う」を大切にする
彼らにとって、「いつもと違う」は単なる偶然ではなく、重要なシグナルです。「なぜ違うのか」を考える習慣が、他の人には見えない問題や機会の発見につながります。
3. 「つなぐ」の習慣
必要な情報を適切に共有する
評価される人は、単に問題を見つけるだけでなく、適切な人に適切なタイミングで伝える能力に長けています。
「これは今すぐ伝えるべき」「これは定例会議で報告すれば十分」という判断が的確です。
困っている人に自然にフォロー
彼らは、同僚が困っているのを見ると自然にサポートします。しかも、相手のプライドを傷つけない絶妙な距離感で。
「手伝おうか?」ではなく「私もこれから同じことをするところだったから一緒にやらない?」というアプローチが上手いのです。
チーム全体の動きを意識する
自分の仕事だけでなく、チーム全体のゴールを意識しています。そのため、自分の担当外のことでも、全体最適のために行動することができます。
今日から始められる「見えない努力」の実践方法
「それって特別な才能じゃないの?」と思われるかもしれません。でも、実はどれも地道な習慣の積み重ねで身につくものです。
「予防」の習慣を身につけるには
- 朝の5分点検を習慣にする メールチェックの前に、前日の重要指標を確認する時間を作りましょう
- **「気になるリスト」**を作る ちょっとした違和感や懸念点をメモしておく習慣をつけましょう
- **週一回の「予防会議」**を自分に課す 週の始めに「今週起こりうる問題は?」と自問する時間を作りましょう
「気づき」の習慣を身につけるには
- 「いつもと違うこと」探しを習慣に 日常の中で「昨日と違うこと」を3つ見つける練習をしてみましょう
- 「なぜ」を3回繰り返す 何か変化に気づいたら「なぜそうなった?」を3回掘り下げてみましょう
- **プロジェクトごとに「重要指標」**を決める 何を見れば異変に気づけるか、重要な指標を事前に決めておきましょう
「つなぐ」の習慣を身につけるには
- 朝の雑談5分を大切に 始業前のちょっとした会話で、チームの状況を把握しましょう
- **「誰が助かる?」**の視点 情報を得たとき「これを知ったら誰が助かるか」と考えましょう
- チーム全体の目標を常に意識 自分の仕事が全体のどこに位置するか、定期的に確認しましょう
なぜ「見えない努力」は評価につながるのか
こうした「見えない努力」が評価につながるのはなぜでしょうか?それには重要な理由があります。
1. 問題の「未然防止」は最大の貢献
問題が起きてから解決するよりも、問題が起きない状態を作ることの方が、実は価値が高いのです。ただし、これは「見えない貢献」になりがちです。
トラブル対応は目立ちますが、トラブルを防いだ人は目立ちません。しかし、真に優れた上司や経営者は、この「予防力」の価値を理解しています。
2. 「小さな違和感」に気づける人は信頼される
「なんとなくおかしい」という感覚を大切にし、それを検証できる人は、組織にとって非常に価値があります。この能力は経験を重ねることで磨かれていくものです。
3. 「つなぐ」能力はチーム全体を強くする
情報を適切に共有し、人と人をつなげられる人は、チーム全体のパフォーマンスを高めます。こうした「触媒」的な役割は、組織が大きくなるほど価値が高まります。
まとめ:小さな習慣が大きな評価を生む
先日、倉庫で古い資料を整理していました。一番下の引き出しから、数年前の改善提案のファイルが出てきました。そこには、Cさんの地道な改善提案がびっしりと記録されていました。
彼女の「見えない努力」は、実はしっかりと記録され、評価されていたのです。
評価される人の習慣は、突き詰めれば「小さなことを大切にする」という姿勢に集約されます。派手な成果や革新的なアイデアだけが評価されるわけではありません。
日々の小さな気づき、さりげないフォロー、未然の予防。これらの「見えない努力」が、長い目で見ると大きな評価につながるのです。
明日から、あなたも「見えない努力」の第一歩を踏み出してみませんか?きっと、周囲の見る目が変わってくるはずです。
この記事はいかがでしたか?もし役立つと感じていただけたなら、ぜひシェアしていただけると嬉しいです。また、あなたが実践している「見えない努力」があれば、コメント欄で教えてください。お互いの知恵を分かち合うことで、さらに成長していきたいと思います。

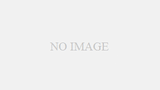
コメント