
「なぜか彼の意見は通りやすい…」
「あの人に頼むと安心できる…」
「彼女がいると、チームの雰囲気が良くなる…」
職場で絶大な信頼を得ている人には、このような特徴があります。この「信頼される力」は、単なる人気とは異なる深い影響力です。そして、最も嬉しいことに、この力は生まれつきの才能ではなく、誰でも身につけられるスキルなのです。
私自身、製造現場のリーダーからWeb担当へのキャリアチェンジの過程で、「信頼関係の築き方」について多くの壁にぶつかり、そして学びを得てきました。特に部下が次々と退職するという厳しい経験から、信頼構築の本質を見つめ直す機会を得たのです。
この記事では、心理学の知見と私自身の経験から導き出した、職場での信頼関係を構築するための9つの実践的テクニックをお伝えします。
目次
- なぜ職場での信頼関係が重要なのか
- 信頼関係構築の9つのテクニック
- テクニック1:「聴く力」を磨く
- テクニック2:「約束の文化」を徹底する
- テクニック3:「適切な自己開示」で距離を縮める
- テクニック4:「一貫性」を保つ
- テクニック5:「承認と感謝」を日常に組み込む
- テクニック6:「意図と影響」のギャップを理解する
- テクニック7:「批判と提案」の言い換え技術
- テクニック8:「心理的安全性」を創り出す
- テクニック9:「修復の機会」を大切にする
- 信頼を損なう行動パターンとその対策
- 信頼関係構築の3つのステージ
- まとめ:信頼は日々の小さな選択の積み重ね
なぜ職場での信頼関係が重要なのか
信頼関係は、単なる「職場の人間関係を良くする」以上の重要な意味を持っています。
信頼がもたらす3つの効果
- 生産性の向上
ハーバードビジネススクールの研究によれば、高信頼組織は低信頼組織と比較して生産性が2.5倍高いという結果が出ています。信頼があると、無駄なチェックや確認作業が減り、本質的な仕事に集中できるからです。 - イノベーションの促進
グーグルの「Project Aristotle」の調査では、チーム内の心理的安全性(信頼の土台)が高いほど、革新的なアイデア創出が活発になることが明らかになっています。信頼がある環境では失敗を恐れず挑戦できるのです。 - レジリエンス(回復力)の強化
危機や変化の際、信頼関係が強いチームほど迅速に適応し、回復することがわかっています。特にリモートワークが増えた現代では、この信頼に基づくレジリエンスがさらに重要になっています。
私自身の経験から
製造部門のリーダーだった私は、成果を追い求めるあまり「結果」にばかり目を向け、「関係性」を軽視していました。その結果、1年間で5人の部下が退職するという痛恨の経験をしました。
この経験から、どれだけ優れた戦略や技術があっても、それを実行するのは「人」であり、人と人との信頼関係なくしては、本当の成果は生まれないということを身をもって学びました。
信頼関係構築の9つのテクニック
では具体的に、職場での信頼関係を構築するためのテクニックを見ていきましょう。
テクニック1:「聴く力」を磨く
信頼関係の土台となるのは「聴く力」です。これは単に黙って聞くことではなく、相手の言葉の奥にある気持ちや考えを理解しようとする姿勢を意味します。
実践方法:
- 積極的傾聴の3段階
- 1段階目:情報を聴く(事実や内容を理解する)
- 2段階目:感情を聴く(言葉の裏にある感情を感じ取る)
- 3段階目:価値観を聴く(なぜそう感じるのか、相手の大切にしているものを理解する)
- 「聴いている」を示す方法
- アイコンタクトを適切に保つ
- 相づち・うなずきを意識的に入れる
- スマートフォンなどの気が散るものを遠ざける
- 相手の言葉を時々言い換えて確認する
心理学的背景:
心理学者のカール・ロジャースは、「傾聴は単なるテクニックではなく、相手を尊重する態度の表れ」と述べています。人間は「理解されたい」という根源的な欲求を持っており、この欲求が満たされると信頼感が生まれるのです。
私の実践例:
Web担当になって間もない頃、若手デザイナーから「このデザイン案、どう思いますか?」と意見を求められました。以前の私なら即座に改善点を指摘していたでしょう。しかし、まずは「このデザインに込めた思いを教えてもらえる?」と質問してみました。
彼の話を聴くうちに、単なるデザインの相談ではなく、「自分の方向性に自信がない」という不安が根底にあることがわかりました。結果的に、デザインへのフィードバックだけでなく、彼のキャリアの方向性についても話し合う貴重な機会となり、その後の信頼関係構築につながったのです。
テクニック2:「約束の文化」を徹底する
信頼の本質は「予測可能性」にあります。相手の行動が予測できるとき、人は安心感を覚え、信頼が生まれます。「約束を守る」という一見シンプルな行動が、実は信頼構築の強力な土台となるのです。
実践方法:
- 小さな約束も必ず守る
- 時間約束(会議、提出期限など)を厳守する
- 「すぐ返信します」と言ったら、実際にすぐ返す
- 「調べておきます」と言ったことは必ず調べる
- 無理な約束はしない勇気を持つ
- できないことには「できません」と正直に伝える
- 代替案を提示する(「今日は無理ですが、明日の午前中ならできます」)
- 断る理由を簡潔に説明する
- 約束を変更する際の3ステップ
- できるだけ早く伝える
- 理由を簡潔に説明する
- 新しい約束を提案する
心理学的背景:
認知心理学では「一貫性の原理」というものがあります。人は自分の過去の言動と一致する行動を取りたいという心理的傾向があるのです。一貫した行動パターンを示すことで、相手の中に「この人は信頼できる」という認知が形成されていきます。
私の実践例:
製造部門でのこと、品質管理の重要な会議で「月曜日までにデータを集計します」と約束したものの、週末に予定外の仕事が入りました。以前の私なら「事情があったから仕方ない」と月曜日に謝るところでしたが、この「約束の文化」を学んだ後は、すぐに上司に電話して事情を説明し、日曜出勤して約束を守りました。
この小さな出来事が、「たかっちの言うことは信頼できる」という評判につながり、その後のプロジェクトリーダーへの抜擢にも影響したと思います。小さな約束の積み重ねが、大きな信頼を生み出すのです。
テクニック3:「適切な自己開示」で距離を縮める
信頼関係を深めるには、お互いをより知る必要があります。「自己開示」は、その距離を縮める効果的な方法です。ただし、ここでいう自己開示とは、単なる個人情報の共有ではなく、自分の考えや価値観、時には弱さも適切に伝えることを意味します。
実践方法:
- 段階的な自己開示
- 1段階目:事実レベル(「私は◯◯出身です」「前職では◯◯をしていました」)
- 2段階目:意見レベル(「このプロジェクトについて、私はこう考えています」)
- 3段階目:感情レベル(「正直、この状況には不安を感じています」)
- 適切な自己開示の基準
- 相手との関係性に応じた深さを選ぶ
- 職場に関連する内容を中心にする
- 自己開示の目的を意識する(単なる愚痴になっていないか)
- 脆弱性の戦略的共有
- 完璧を装わず、適切な「失敗談」を共有する
- 助けを求めることを恐れない
- 自分の限界や不得意分野を正直に伝える
心理学的背景:
社会心理学者のシドニー・ジュラードは「自己開示の互恵性」という概念を提唱しています。人は自己開示をしてくれた相手に対して、同じように自己開示をしたくなる傾向があるのです。また、適切な脆弱性の共有は「人間的親近感」を生み、信頼を深める効果があります。
私の実践例:
Web担当として異動したばかりの頃、チームミーティングで正直に「SEOについてはまだ勉強中です。皆さんの知識を借りながら一緒に進めていきたい」と伝えました。当初は「弱みを見せるのは危険」と思いましたが、意外にもこの正直さがチームの信頼を得るきっかけになりました。
若手社員が「自分も実はここがわからない」と発言しやすい雰囲気が生まれ、全体のスキルアップにつながったのです。適切な脆弱性の共有は、むしろリーダーとしての信頼を高める効果がありました。
テクニック4:「一貫性」を保つ
人が最も信頼を感じるのは、相手の言動に「予測可能な一貫性」がある場合です。逆に、その場の状況や相手によって態度が変わる人は、どれが本当の姿なのか判断できず、信頼を損ねがちです。
実践方法:
- 価値観の明確化
- 自分の核となる価値観(例:公平性、誠実さ、質の高さなど)を明確にする
- その価値観をチームに伝え、行動の指針としていることを示す
- 判断に迷ったとき、この価値観に立ち返る
- 一貫したコミュニケーションパターン
- 良いニュースも悪いニュースも同じトーンで伝える
- 部下全員に対して同じ基準を適用する
- 会議での発言と、個別の会話に矛盾がないようにする
- 感情コントロール
- ストレス下でも冷静さを保つ訓練をする
- 感情的になりそうなとき、一呼吸置く習慣をつける
- 自分の「引き金(トリガー)」を理解し、事前に対処法を考えておく
心理学的背景:
社会心理学の「帰属理論」によれば、人は相手の行動を観察して、その人の人格や意図を判断します。一貫した行動パターンがあると、相手は「この人はこういう人だ」と理解しやすくなり、その結果として信頼感が生まれやすくなるのです。
私の実践例:
製造現場のリーダー時代、納期が迫る中で品質問題が発生したことがありました。周囲は「今回は少し基準を下げても出荷しよう」と主張しましたが、私は常日頃から「品質は妥協しない」と言っていたため、この状況でもその姿勢を貫きました。
結果として納期は少し遅れましたが、この判断がチームからの信頼につながりました。「たかっちは、どんな状況でも自分の言葉に責任を持つ人だ」という評価を得ることができたのです。一貫性は時に短期的な不利益をもたらすこともありますが、長期的な信頼構築には欠かせない要素です。
テクニック5:「承認と感謝」を日常に組み込む
信頼関係を育む上で、相手の存在や貢献を認め、感謝の気持ちを伝えることは非常に効果的です。これは単なる「褒める」という行為ではなく、相手の価値を認識し、それを適切に表現するスキルです。
実践方法:
- 具体的な承認
- 漠然とした褒め言葉ではなく、具体的な行動や成果を指摘する
- 「よくやった」ではなく「あのプレゼンで、データを視覚化した部分が特に効果的だった」
- その行動がもたらした影響にも触れる
- 日常的な感謝の表現
- 小さな協力や支援にも「ありがとう」と言葉にする
- なぜ感謝しているのかを添える(「あなたのサポートで、期限内に完成させることができました」)
- 口頭だけでなく、時にはメールやメモでも残す
- 承認の「ダブルタップ」
- 公の場での承認と、個人的な場での承認の両方を行う
- チーム全体への貢献を組織的に認める機会を作る
- 承認を習慣化する(例:週次ミーティングで必ず「今週のグッドジョブ」を共有)
心理学的背景:
行動心理学の「強化理論」によれば、承認や感謝といったポジティブなフィードバックは、その行動を強化し、継続させる効果があります。また、「社会的交換理論」では、感謝の表現は「心理的負債」を生み出し、互恵的な関係構築につながるとされています。
私の実践例:
Web担当になって間もない頃、若手社員がデータ分析で見落としていた重要な傾向を指摘してくれました。私はミーティングの場で「〇〇さんのおかげで、このトレンドに気づくことができました。この発見は今後の戦略に大きく影響します」と具体的に伝えました。
さらに後日、1対1の場面でも「あの指摘は本当に価値があった。私自身が見落としていたポイントだし、チーム全体の視野を広げてくれた」と改めて伝えました。
この「ダブルタップ」のアプローチにより、彼はその後も積極的に意見を出すようになり、チーム全体の雰囲気も変わっていきました。適切な承認は、相手の自信だけでなく、あなた自身への信頼感も高めるのです。
テクニック6:「意図と影響」のギャップを理解する
私たちの言動が相手に与える影響は、自分の意図とは異なる場合があります。このギャップを理解し、自分の言動が相手にどう受け取られるかを意識することが、信頼関係構築には欠かせません。
実践方法:
- 相手の視点に立つ訓練
- 自分の発言や決定を、相手の立場から想像してみる
- 特に権力関係がある場合(上司-部下など)、そのバイアスを考慮する
- 自分の言葉が「最善の解釈」ではなく「最悪の解釈」をされた場合を想定する
- フィードバックを求める習慣
- 「私の伝え方で、もっと良い方法はありますか?」と定期的に尋ねる
- 1対1のミーティングで、コミュニケーションについて話し合う時間を設ける
- 信頼できる同僚に、自分の言動の印象を聞く
- 影響に責任を持つ
- 意図せず相手を傷つけたり不安にさせた場合、素直に謝罪する
- 「そんなつもりはなかった」と意図を主張するのではなく、相手の感情を受け止める
- 今後の改善策を具体的に伝える
心理学的背景:
社会心理学の「根本的帰属の誤り」という概念があります。これは、自分の行動は状況要因で説明し(「時間がなかったから」)、他者の行動は性格要因で説明する(「彼はいい加減だから」)という認知バイアスです。このバイアスを理解することで、相手の行動をより公平に解釈できるようになります。
私の実践例:
Web担当になって初めてのプロジェクトミーティングで、あるアイデアに対して「それは難しいと思います」と即座に反応してしまいました。後で若手社員から「アイデアを出すのが怖くなった」という声を聞き、自分の意図(「実現可能性を考えていた」)と影響(「新しいアイデアを抑制してしまった」)のギャップに気づきました。
次のミーティングで、「先日は皆さんのアイデアに対して否定的な反応をしてしまい、申し訳ありませんでした。これからは『どうすれば実現できるか』という視点で一緒に考えていきたいと思います」と伝えました。この正直な対応が、むしろチームからの信頼を高めることになりました。
テクニック7:「批判と提案」の言い換え技術
信頼関係は、困難な状況や意見の対立をどう乗り越えるかによって、その強さが試されます。特に「批判」をどう伝えるかは、信頼構築の重要なポイントです。
実践方法:
- 批判から提案へのフレーム変換
- 「それは間違っている」→「こうするとより効果的かもしれない」
- 「なぜこうなったの?」→「今後こうならないために何ができるだろう?」
- 「そのアプローチには問題がある」→「別の角度からも検討してみては?」
- 「私メッセージ」と「事実ベース」の組み合わせ
- 「あなたは遅い」→「このタスクは予定より3日遅れています。私はこの遅れが気になっています」
- 「あなたの説明は分かりにくい」→「私はこの部分が理解できませんでした。もう少し詳しく説明してもらえますか?」
- 「やる気がないように見える」→「最近、ミーティングでの発言が減ったように感じます。何か支援できることはありますか?」
- 「サンドイッチ法」の改良版
- 単に褒め→批判→褒めではなく、「特定の強み」→「改善提案」→「期待と支援」の構造にする
- 「あなたのデータ分析能力は素晴らしい」→「このプレゼン資料はもう少し簡潔にするとインパクトが増すかも」→「あなたの分析力を活かせば、きっと素晴らしい資料になると思う。必要なら一緒に考えよう」
心理学的背景:
神経科学の研究によれば、批判を受けると脳は「戦うか逃げるか」という防衛反応を示します。これは生存本能の一部ですが、防衛状態では創造的思考や関係構築が阻害されてしまいます。フレーム変換や「私メッセージ」は、この防衛反応を最小限に抑え、建設的な対話を可能にする効果があります。
私の実践例:
製造現場時代、品質管理の担当者が重要なチェックを見落としたことがありました。以前の私なら「なぜ基本的なことができないんだ」と叱責していたでしょう。しかし、「私メッセージ」を使って、「この見落としでライン全体が止まってしまい、私は焦りました。このチェックを確実にするために、どんな工夫ができると思いますか?」と伝えました。
すると彼は防衛的になるのではなく、「チェックリストの改善とダブルチェック体制を提案します」と建設的な回答をしてくれました。批判ではなく提案としてフレーミングすることで、問題解決に焦点を当てた建設的な対話が生まれたのです。
テクニック8:「心理的安全性」を創り出す
「心理的安全性」とは、グーグルの調査で高パフォーマンスチームの最も重要な特徴として特定された概念です。これは「意見を言ったり、質問したり、ミスを認めたりしても、恥をかかされたり罰せられたりしない」という確信がチーム内にある状態を指します。
実践方法:
- リーダーからの脆弱性の表現
- 自分の過去の失敗や学びを共有する
- 分からないことを素直に「分からない」と認める
- 助けを求めることを恐れない
- 失敗を学習の機会として扱う
- 「誰のせいか」ではなく「何を学べるか」にフォーカスする
- 「失敗学習セッション」を定期的に行い、失敗からの学びを共有する
- 失敗に対して感謝を表現する(「この失敗のおかげで、大きな問題を未然に防げました」)
- 発言障壁を下げる工夫
- 会議での「ラウンドロビン」(全員が必ず一言話す)の実施
- 「まだ完全に固まっていないアイデア」を出し合う時間の設定
- オンライン投票や匿名フィードバックなど、様々な意見表明の手段を用意
心理学的背景:
エイミー・エドモンドソン教授の研究によれば、心理的安全性が高いチームでは「学習行動」(質問する、助けを求める、新しいアイディアを試す)が活発になり、結果としてイノベーションと生産性が向上します。これは個人の能力以上に、チームの相互作用の質が成果に影響することを示しています。
私の実践例:
Web担当として新しいプロジェクトを任された際、チーム全員に「私はこの分野の専門家ではないので、皆さんと一緒に学んでいきたい」と正直に伝えました。そして初回ミーティングで「このプロジェクトで最も心配なことは何ですか?」と全員に質問しました。
最初は沈黙がありましたが、私から「私自身の最大の心配は、技術的な専門知識が足りないことです」と正直に話すと、徐々に全員が率直に懸念を共有し始めました。この「脆弱性の共有」から始まったプロジェクトは、問題が起きても迅速に共有され、皆で解決策を考える文化が生まれ、最終的に大きな成功を収めることができました。
テクニック9:「修復の機会」を大切にする
どんなに信頼関係が強くても、誤解や対立、失敗は必ず起こります。実は、これらの「亀裂」をどう修復するかが、信頼関係をさらに強化する重要な機会となります。上手く対処されたコンフリクトは、むしろ信頼を深める触媒となるのです。
実践方法:
1.迅速な対応
- 問題が小さいうちに対処する
- 亀裂が生じたと感じたら、先延ばしにせず対話の機会を作る
- 「明日話そう」ではなく「今、少しだけ時間をもらえますか?」
2.「責任の100%ルール」の実践
- たとえ相手にも非があると感じても、まずは自分の責任部分を100%認める
- 「あなたが~だから」という言い方を避ける
- 具体的な謝罪と今後の改善策を伝える
3.修復の3ステップ
- 認識: 何が起きたかを明確に認識し、相手の感情を理解する
- 承認: 自分の行動と、それが相手に与えた影響を認める
- 行動: 具体的な修復行動とともに、再発防止策を提案する
心理学的背景:
対人関係の研究によれば、長期的に健全な関係を維持できるカップルの特徴は「完璧な関係」ではなく「修復能力の高さ」だということがわかっています。これは職場の人間関係にも応用できる原則です。修復のプロセスを経験することで、むしろその関係はより強固になるのです。
私の実践例:
Web担当として初めての大きなプロジェクトで、データ分析の際に重要な指標を見落とし、チームに余計な作業を発生させてしまったことがありました。すぐにチームを集め、「私のチェック不足で皆さんに負担をかけてしまい、申し訳ありません。今後はこのようなミスを防ぐために、分析前のチェックリストを作成します」と率直に謝罪しました。
この対応が逆に信頼を深めることになり、チーム全体の「失敗から学ぶ文化」が強化されました。一人のメンバーが「たかっちさんのようなベテランでも間違えることがあると知って、失敗を報告しやすくなりました」と言ってくれたのは嬉しい驚きでした。
信頼を損なう行動パターンとその対策
どれだけ信頼構築に努めても、特定の行動パターンが繰り返されると、信頼は次第に損なわれていきます。これらを意識的に避けることも、信頼関係維持には欠かせません。
信頼を損なう5つの行動
- 一貫性の欠如
場面や相手によって態度や言うことが変わる。 対策: 核となる価値観を明確にし、それに基づいた一貫した判断を心がける。迷ったら「自分の原則は何か」と自問する。 - 情報の隠蔽
必要な情報を共有せず、「知らなかった」と言われる状況を作る。 対策: 「この情報を知らないと困る人は誰か」を常に考え、プロアクティブに情報共有を行う。定期的な情報共有の場を設ける。 - 約束不履行
期限や品質の約束を守らず、言い訳をする。 対策: 「約束の文化」を徹底し、無理な約束はしない勇気を持つ。問題が発生しそうなら早めに共有し、代替案を提示する。 - クレジットとブレームの不均衡
成功は自分の手柄、失敗は他人のせいにする。 対策: 「成功はチームに、失敗は自分に」という原則を守る。他者の貢献を積極的に認め、自分の責任部分を明確に認める。 - 陰口と非難
不在の人について否定的な発言をする。 対策: 「その人がここにいたら、同じことが言えるか」というテストを常に行う。問題があれば直接本人と話し合う。
自己診断の方法
自分が無意識に信頼を損なう行動をとっていないか、以下のチェックリストで定期的に確認してみましょう。
- 最近、「言っていることとやっていることが違う」と指摘されたことはないか
- 「知らなかった」という言葉を頻繁に使っていないか
- 約束した期限を変更することが多くなっていないか
- 成功の際に関わった全員の貢献を認めているか
- 人がいないところでその人について話していることは、本人の前でも言えるか
これらの質問に「はい」と答えにくい項目があれば、それは信頼関係に亀裂が生じる可能性のあるポイントです。早めの意識改革が必要でしょう。
信頼関係構築の3つのステージ
信頼関係は一朝一夕に築けるものではなく、いくつかのステージを経て徐々に深まっていきます。それぞれのステージを意識することで、今自分がどこにいるのか、次に何をすべきかが見えてきます。
ステージ1:「予測可能性」の信頼(基本的信頼)
このステージでは、相手の行動がある程度予測できることに基づく初期的な信頼関係が形成されます。
特徴:
- 「約束を守る」という基本的な信頼
- 一貫した行動パターンによる安心感
- 明確な期待値の共有
取り組むべきこと:
- 自己紹介や簡単な自己開示でスタート
- 小さな約束を確実に守る実績を積み重ねる
- 基本的な職場ルールと期待値を明確にする
この段階でよくある課題:
- 表面的な関係に留まりがち
- 本音が出にくい
- 形式的なコミュニケーションが中心
ステージ2:「能力」への信頼(専門的信頼)
相手のスキルや判断力、問題解決能力を信頼する段階へと発展します。
特徴:
- 専門性やスキルへの相互認識
- 役割と貢献の明確化
- 協働作業の実績
取り組むべきこと:
- お互いの強みと弱みの理解を深める
- 具体的なフィードバックの共有
- 共同で困難な課題に取り組む機会を作る
この段階でよくある課題:
- 能力評価に偏りがち
- 失敗への恐れから挑戦を避ける
- 競争意識が生まれることも
ステージ3:「意図」への信頼(人格的信頼)
最も深い信頼関係は、相手の意図や価値観、人格そのものへの信頼に基づきます。
特徴:
- 相手の動機や価値観への理解と共感
- 感情や個人的な課題も共有できる関係
- 厳しい状況でも信頼が揺らがない
取り組むべきこと:
- より深い自己開示と価値観の共有
- 対立や危機を共に乗り越える経験を積む
- 互いの成長を支援し合う関係を育む
この段階でよくある課題:
- 到達するまでに時間がかかる
- 一度崩れると修復が難しい
- 過度に親密になりすぎるリスク
まとめ:信頼は日々の小さな選択の積み重ね
信頼関係を築くための9つのテクニックをご紹介してきましたが、最も大切なのは「信頼は日々の小さな選択の積み重ね」だということです。
一度の大きな行動ではなく、毎日の少しずつの選択が、やがて揺るがない信頼の基盤となります。
- 「今日は少し時間を取って、彼の話をじっくり聴こう」
- 「この約束は必ず守ろう」
- 「不安な気持ちも正直に伝えてみよう」
- 「ミスをしたら、すぐに認めて修復しよう」
こうした小さな選択の積み重ねが、信頼という目に見えない資産を築いていくのです。
私自身、製造現場のリーダーからWeb担当へのキャリアチェンジの過程で、信頼関係構築の大切さを身をもって学びました。新しい環境で一からの信頼構築は簡単ではありませんでしたが、この記事でご紹介したテクニックを一つずつ実践することで、徐々に関係性を深めることができたのです。
信頼関係の構築には時間がかかります。すぐに結果が見えないこともあるでしょう。しかし、この投資は必ず報われます。信頼に基づいた関係性からは、創造性、生産性、そして何より仕事の喜びが生まれるのですから。
明日から、あなたも小さな一歩を踏み出してみませんか?
この記事は役に立ちましたか?もし参考になれば、ぜひシェアしていただければ嬉しいです。また、あなた自身の職場での信頼関係構築の体験や工夫があれば、コメント欄でぜひ教えてください。

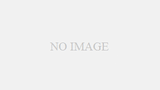
コメント